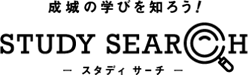地方自治のグローバル化
近年では地方公共団体の事務のグローバル化が進んでおり、例えば、外国人参政権を認めるかどうかという問題が例として挙げられます。ここでは武蔵野市住民投票条例を素材に考えてみたいと思います。

武蔵野市住民投票条例案
武蔵野市では、外国人に住民投票権を認めるかどうかが議論されています。案として出されたのは、3ヶ月以上住所を有する定住外国人にも住民投票権を認めるものです。ここでは主に①外国人に住民投票権を認めることはできるか?②住民投票に法的な拘束力を認めてもよいか?という点が問題となります。
外国人投票権
地方公共団体の選挙権が問題となった判例(最判平成7年2月28日民集49巻2号639頁)は、「永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」に選挙権を与えることは憲法上禁止されないと示しました。これに対し、条例案は「武蔵野市に住所を有する18歳以上の者」に投票権を認めており、一定期間(3ヶ月)以上の居住から「住民」であることが基礎づけられます。住民投票を選挙と同視できるかは住民投票の法的拘束力を認めるかでも異なりますが、居住期間のみから「特段の緊密な関係」を基礎づけてもよいかという点については、評価が分かれるでしょう。

住民投票の法的拘束力
現在では、代表民主制が原則であり、直接民主制である住民投票に法的拘束力を認めない見解が有力です。これに対し、条例案によれば、市は「住民投票の結果を尊重する」とされています。市の説明によれば、法的拘束力がないとされている一方で、実質的には拘束力があるともされています。この場合、市の判断に際して、住民投票の結果と異なる決定をすること自体は許されますが、住民投票の結果を全く考慮しない場合には違法になりえます。もっとも、これは法的拘束力を認めていることと同じように思われるところです。