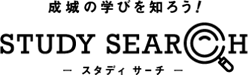ステレオタイプとは?
みなさんは「高齢者」と聞いて、どのようなことを思い浮かべるでしょうか。頑固、病弱、優しい、知恵がある…などかもしれません。このように、特定の集団に属する人々に対して、社会的に広く共有されている信念やイメージのことを「ステレオタイプ」と呼びます。例えば、あなたが高齢者と出会ったときに「高齢者なのに、とても元気だ」と感じたとしたら、それは事前に「高齢者=病弱」というステレオタイプを持っていた可能性があります。
ステレオタイプ、偏見、差別
このようなステレオタイプは、しばしばネガティブな感情を伴うことで「偏見」となり、さらにそれが行動として表れることで「差別」となります。例えば、「高齢者は病弱だから仕事ができないだろう。だから自分の会社では雇わない」と考え、年齢だけに基づいて採用や昇進の機会を制限することは、差別にあたります。

ステレオタイプの良い側面?
もっとも、ステレオタイプを一概に悪いものだと決めつけることはできません。なぜなら、私たちは常に膨大な情報の中で暮らしており、ステレオタイプはその情報処理を助ける役割を持つからです。もし、初めて会うすべての人に対して、「どんな人だろう」「何が好きなのだろう」と丁寧に情報を処理しようとすれば、私たちはすぐに疲れてしまうでしょう。こうしたとき、ステレオタイプは瞬時の意思決定を助けてくれるのです。
結局、どうしたらよいのか
では、ステレオタイプとどのように向き合えばよいのでしょうか。明確な答えがあるわけではありませんが、私が大切だと思うのは、「自分はステレオタイプを持ったまま他者と接している」という事実を意識することです。なかには「私は他者を色眼鏡で見ることはしない」と断言する人もいますが、ステレオタイプを完全になくすことは極めて困難です。多かれ少なかれ、私たちは他者をステレオタイプ的に捉えてしまうものです。だからこそ、「自分は無意識のうちに先入観を持って他者に接しているかもしれない」と心に留めておくことが大切なのではないでしょうか。