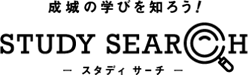戦争の勝利がもたらした高揚
日露戦争(1904~05年)は、20世紀初めの東アジアにおける勢力争いを象徴する出来事です。日本とロシアは、この戦争で双方の見方を大きく変えました。それからも、両国の「この戦争をどう語るか」は大きく揺らぎ、変化しています。日露戦争の直後から昭和の戦前には、日本ではこの戦争は国家と国民が一丸となった「聖戦」「祖国防衛戦争」として語られました。また、「有色人種が白人の大国を打ち負かした歴史的偉業」として、人種の観点からも語られていました。
敗北が変えたロシアの運命
一方、日露戦争後のロシアと第二次世界大戦前のソ連では、日露戦争は帝政末期のロシアの弱体さを露呈し、国内の不満と革命情勢を加速させたと語られてきました。敗戦は帝政崩壊やロシア革命の前段階の文脈で注目されてきたと言えるでしょう。

戦後、大きく変わった歴史の解釈
第二次世界大戦後、日本では、従来の日露戦争の勝利を賛美する歴史観を問い直す動きが出てきます。戦争の犠牲となった兵士たちや、アジア諸国の視点、帝国主義的な側面を歴史教育や学界で取り上げる動きも顕著になります。特に日露戦争後に植民地となった朝鮮半島への着目は、戦争への見方を変えました。近年では、文学や新聞といったメディア論や、記念碑など戦争の表象についても研究が進んでいます。第二次世界大戦後のソ連でも、歴史観を見直す流れの中で、日露戦争に対する評価が再編されます。従来のロシア帝国への批判的観点に加え、国際史的視点を通じて、戦争の原因・外交・軍事戦略を冷静に検証する歴史研究が進みました。ソ連崩壊後はこの流れが加速する一方、近年は愛国主義の高まりから、日露戦争の「英雄」を顕彰する動きが強まっています。また困難な日露関係のなかで、ロシアは歴史の語りを外交カードとしても用いる傾向があるのには注意を要します。

今を映す鏡として歴史を捉える
こうした変遷を比べると、歴史認識とは固定的なものではなく、時代の政治・社会・外交の状況や、学問の進展とともに揺れ動くものだということがわかります。これからも日露戦争の語りは、その時代に応じて変化してゆくでしょう。