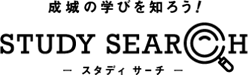ママチャリは日本独自の文化
日本は世界的にみても自転車の交通分担率が高く、とりわけ女性の自転車利用率が極めて高いことで知られています。その象徴が「ママチャリ」と呼ばれる自転車で、日本ではごく普通に見られるこのような自転車は、実は世界ではあまり類のない独自のものです。必ずしも女性ばかりが利用するわけではありませんが、「女性が使いやすい」ことをデザインコンセプトとするこの種の自転車は、私たちが普段は省みることの少ない「当たり前」の社会規範を考察するのに恰好の素材です。
ママチャリの進化が日本女性の役割の変化を示す
歴史的にみても、自転車が普及し始めた明治時代から、日本では女性の利用が比較的広く見られました。そして戦後になると、女性が乗りやすいように車体のデザインが改良され、買い物や子どもの送迎に便利なようにカゴやチャイルドシートが標準装備され、近年では電動化によって脚力の不足も補われることになりました。こうしたママチャリのデザインと機能の変化は、時代ごとの生活空間の編成や女性の社会的役割の変化に呼応しています。

車でも歩行者でもない、揺れる自転車の立場
一方で、自転車は道路上では歩行者と自動車の双方にとって異質な存在で、その位置付けは多くの議論を呼びます。例えば、自転車は道路のどこを走るべきかについては、道路交通法の上でも二転三転しています。近年は視覚的な表示をすることで、車道の左端を通行すべきことを明示していますが、そこが子どもを乗せた女性などが走るのに快適な空間であるとはまったく思われていないようで、歩道通行は常態化したままです。他にも最近では、ヘルメットの着用の努力義務化が話題になりました。確かにヘルメットの着用は事故が起こった際の安全性を高めるでしょう。しかし、義務化はとくに女性が自転車に乗るのに心理的な抵抗を与えます。世界的な自転車普及の先進国であるオランダやデンマークでは、街中で自転車に乗る人がヘルメットを被っている姿はあまり見られません。

自由度のある使いやすさと安全性を考える
このような観察から、法律や規則で規定されるばかりでなく、人びとの日常生活の経験から培われる秩序について考えるとともに、それをどのように実質的に運用し、安全性と利便性を高められるかを考えることが求められます。